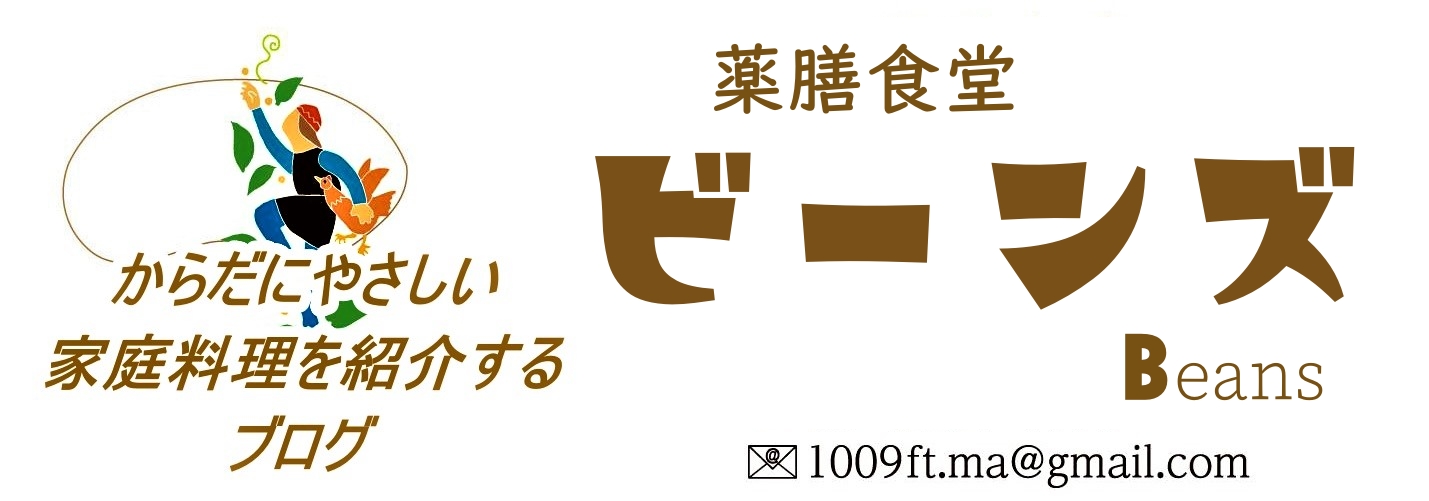蓮の実は夏の終わりから初秋に実り、精神不安やイライラを鎮める働きがあります。
肺を潤して咳予防になる白木耳(しろきくらげ)と無花果(いちじく)を合わせてデザートにしました。
お砂糖を使わず、メープルシロップで甘味をつけます。
メープルシロップにも肺を潤す作用があります。
蓮の実について
蓮は花が咲いたあと9~10月に実を結びます。
薬膳では、蓮子(リェンツ)と呼ばれ、心の機能を正常にし、精神を安定させ、腎機能を保養し、尿漏れ、下痢を改善するにのに利用します。
中心部にある芯(子葉)は、蓮子芯(リェンズシン)と呼ばれ、苦味が強いが、心を安定させ、熱を下げ止血、早漏に利用されます。
雄蕊は蓮鬚(リェンシュ)と呼ばれ、実と同様の薬効があります。

花托(かたく)は乾燥させ、炙ったものが止血に使われます。
葉は、荷葉(フイェ)と呼ばれ、清暑利湿(暑さによる気と体液の消耗を防ぎ、湿を除き水分代謝をよくする)、昇陽止血(消化機能を助け、出血を防ぐ)に利用されます。
実の乾燥品の場合は水に20~30分つけて戻してから使います。

白木耳(しろキクラゲ)について
木耳はキノコの1種、乾燥によってエルゴステリンがビタミンDに変化、カルシウムの吸収を促し、骨を丈夫にします。食物繊維も豊富で、腸内環境を調え、便秘を改善。
薬膳では、滋陰潤肺(体液を補い、肺を潤す)、養胃(消化機能を養う)、生津(体液を補う)などにに利用します。

無花果(いちじく)について
茎の切口から出る白い液にはタンパク質を分解する酵素フィシン、果肉には脂肪分解酵素リパーゼ、デンプン分解酵素アミラーゼを含み、胃腸での消化吸収を助けます。
また、水性食物繊維のペクチンがコレステロールや老廃物を排出し、便秘解消に役立ちます。
薬膳では、潤肺止咳(肺を潤し、咳止め)、開胃(消化機能を正常化)、利喉(喉の腫れや痛みを改善)などに利用します。

メープルシロップについて
楓の樹液を煮詰めたもので甘味料になります。
蜂蜜よりビタミン、ミネラル類を多く含み、抗酸化、抗老化作用があります。
薬膳では、生津(体液を補う)、清肺(肺機能を正常化)、潤肺(肺を潤す)、潤腸(腸を潤し、便秘改善)などに利用します。

材料
(4人分)
蓮の実(生) 40g
白木耳(乾燥) 10g
(もどすと約10倍)
無花果 4個
メープルシロップ
大さじ3~4
作り方
1.花托(かたく)に切り込みを入れて蓮の実を取りだします。

2.白木耳は多めの水に約30分浸してもどします。
3.蓮の実の緑色の皮をむき、半分に割り、芯は苦いので除きます。
芯、花托にも薬効があるので残しておきます。

4.もどした白木耳を鍋に入れ、ざっとほぐし、水1ℓを加えます。
中火のかけ、沸いたら弱火にして柔らかくなるまで約1時間煮ます。

5.無花果は成口の茎を除き、縦8つに切ります。

6.白木耳が柔らかくなったら、蓮の実と無花果を加え、軽く火を通し、メープルシロップで甘味をつけます。

紹介動画
以下の画像をクリックすると動画で観ることが出来ます。

本日のご紹介はいかがでしたでしょうか?
この他にも家庭でできる簡単レシピなど紹介しています。
ご家庭でもぜひお試しください!